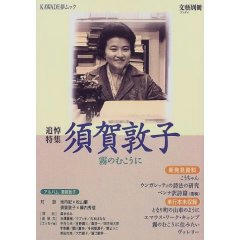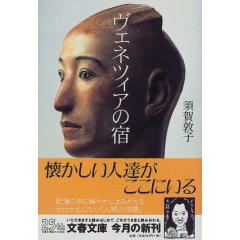| マルコおいちゃんのドイツ生活ああだこうだ事典 |
| ≪Bar di Marco≫から旧名に復帰しました。 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
世界中を妖怪が徘徊しているようである、スターバックスという妖怪が。
そしてなにやらイタリアン・コーヒーというなにやら怪しげなイメージを振りまくことに猖獗を極めているらしい。
そんなものがある、という認識のレベルに事を収めておきたい。
イタリアで、Caffèを飲むところといえば、「Bar」である。
といってもいわゆる「バー」ではなく、ちいさな「カッフェー」と思っていただければよい。
そのバリーエションには限りがなく、カウンターだけのものから、店内はもとより道路まで椅子席を張り出したものまで、無数の形態がある。
しかし、唯一共通項を捜すとすれば、エスプレッソ・マシーンであろう。いまさら写真を紹介するまでもなかろう。
つまるところ、エスプレッソ(espresso)、すなわちCaffèである。あなたがイタリアの「Bar」に入って、「un Caffè」と注文すれば、エスプレッソが出てくる。
エスプレッソとは何であるかは、これもいまさら説明は要すまい。
一度、マヨルカ島の小さなカッフェーで、「エスプレッソ」と注文したが、通じなかった。まるでラファエロ描くところの美少女のような、亜麻色の髪と透き通るような肌をもった女の子の給仕であった。
しかし妻の手前、じっと見とれていることもならず、「Caffè Italiano」とイタリア語でいってみた。(吾輩はスペイン語もカタラン語も解さん)
件の美少女が、にっこりうなずいてわかってくれたのは言うまでもない。
もちろんちゃんとエスプレッソがでてきたよ。
すなわち、かくの如く、エスプレッソがイタリアのコーヒーの代名詞であるということである。
ちなみに、カプチーノというものがあるが、あれは老人や子供が朝に飲むものである。
昼間や夕方、すなわち朝以外の時間に、ましてや大の大人がカプチーノなんぞという代物を、イタリアの「Bar」で注文してはならんのだ。
すぐに外国人だとばれてしまう。まあ日本人ならどうせ見ればすぐばれてしまうのであろうが。
ギンズブルグの『ある家族の会話』には、その家族だけでつうじる言葉についての描写がありました。
ある親密な共同体、たとえば家族のようなものですが、おのずと言葉にしなくてもつうじる物事があります。それは隠語や符牒のようなもので理解しあえる言語環境がかもし出される、ということでしょうか?
家内の家族では、ある季節、すなわち晩春の一時期なのですが、そのころになると、誰からともなく「あの場所(der Ort)は、どうなっているだろうか?」、「あの場所へいってみよう」と語りはじめるのが常となっています。
その場所とは、家からはかなり離れた別の街の郊外にある森の、そのまたはずれにある、ある斜面なのです。
そこは小さな桃園なのですが、そこを訪れる目的は、桃の花でも実でもありません。
そこは南向きの緩やかな斜面になっていて、四月になると、桃の花も散り、桃の木の下にさまざまな野草がいっぱいに咲きそろうのです。
なかでも、「Sclüsselblume」(鍵の花)といわれる、辞書では「サクラソウ類の花」「プリムラ」などとでていますが、どうも全然ちがうものにしか思えない、その野草が豊富に咲きそろうのです。いちど、だむエリちゃんにささげたあの花です。
亡くなった義父が、とくにこの花を愛で、その季節になるといても立ってもいられず、その場所へと赴き、大好きなブルックナーを口笛で奏でながら、まるで少女のように嬉々としてその花を手折って小さなブーケを作り、そしてそれを義母に大げさな身振りで捧げる、ということをしておりました。
いまはそれも思い出、その共通の思い出が、また家族を結びつける絆にもなっているのです。
義父が亡くなってからは、あまりそこへ出かけることもなくなりました。もういない人の思い出に哀しくなるせいかも知れません。
この復活祭の日曜日、誰からともなく、「あの場所はどうなっているだろう?」「行ってみようか?」という話がでて、そして数年ぶりに、その場所へそろってでかけることになりました。
その場所は、その場所のようにあるべき形をしてわれわれを迎えてくれました。
われわれ家族はその場所にすわって語り合い、共通の思い出を胸にしながら、午後の長い時間をすごしたのでした。
義父の亡くなったときはまだ幼く、その記憶もうつろな豚児も、なぜかその場所が気に入ったようで、一人でながいことその場所で遊んでいました。
その場所が、われわれ家族にとっての「アルカデイア」ということを、知らずに感じ取っていたのでしょうか・・・・?
シクラメンというと、すぐに小椋桂の≪シクラメンのかほり≫を思い起こす世代としては、この花には特別な、しかし抽象的な思い入れがあるものです。
あのころは、特別な社会状況で、といっても特別でない社会状況などあるはずもありませんが、たとえば新宿西口広場のファーク・ゲリラが規制されて、西口通路となってからも、柱の陰で自作の詩集を売る少女、なんてのも見られたものでした。
小椋桂の唄には、そのころの雰囲気が染み付いていてなんだか鬱陶しく、今はまったく聴くこともありません。
それは惨めだった自己の「青春」時代を思い出したくない、という思いもこもっているのでしょうか?しかし、明るく爽やかで幸福にみちた青春なんてものがあったら、ぜひ拝見したいものです。
そのもっと以前にTVでいわゆる「青春物」が流行って、泥だらけのいかにも汗臭そうな体育系が、「これが青春だ!」なんて叫んだりしていたものです。ああやだやだ。
それに比べれば、小椋桂の唄はまだまだ甘さがあるものの、少しはナイーヴなセンチメンタリスムがあって、それなりに受けていたように思います。
ところで小椋桂ってご存知?
まあいいや、本題はシクラメンでした。
この春に撮影した野生のシクラメンを紹介しようと書き始めて、ずいぶんと余計なことをしゃべってしまったようです。
あしからずお許しください。以下の写真がそうです。
あなかしこ
マルコ軽薄(敬白の誤りか?)
花はかなり小さく、せいぜいが2センチ弱というところでしょうか。この花を、みちこさんに捧げます。
人気blogランキングへ参加しました。よろしければ応援のクリックをお願いします。
【再録に当たって】
こうして再録しようと再読してみて、イザ版の趣旨から激しく浮き上がっているのがわかります。ゆえにアクセス数も少なかったようです。こんな文章を実は書きたいのですが、イザ版ではなかなか勇気がいります。この点からも別館を開いてよかったなあ、と思っています。再録に際し、若干の字句を改めました。
以前、『イタリア夜想曲』の訳者としてその名前をあげ、さらに後ほど詳しく述べると予告した須賀敦子さんの作品との出会いを前回述べました。
がしかし、後になってわかったのですが実はその前に、『ある家族の会話』ナタリア・ギンズベルグ著、白水社を読んでいたのです。それは須賀さんの和訳でした。その本は、イタリア好きのあたしのために家内がある年の誕生日に送ってくれたものでした。まだ東京に二人で住んでいた頃のことです。
あたしは基本的に翻訳書というものを好みません。いつも変な日本語にあって辟易するからです。後に自分で少し翻訳をするようになってその苦労もわかるようになりましたが、しかしこの『ある家族の会話』にはなにも違和感がなく、いい日本語だなと思ったことを覚えていたばかりで、訳者の名前は記憶していませんでした。きっと立派なイタリア文学研究者なのだと思うばかりでした。
須賀敦子―霧のむこうに
今はしかし、その「小説」の世界にもどりましょう。
続けて『コルシア書店の仲間達』『ミラノ霧の風景』『トリエステの坂道』と書かれた順番も無視して読み続けたのち、彼女の作品があたしをつかまえる理由もうすうす理解できてきました。
それは彼女の運命と文章を発語するにいたったその内的経緯だったのです。人は何故小説を書くのか?作家それぞれがその答えを示してくれますが、須賀さんほど特異な例があるでしょうか?
それは多分「神」がお導きになったものとしか思えません。あたしは仏教徒で須賀さんのようにカソリックの神は信仰しません。がしかし、「神」がお導きになった、須賀さんご自身がそうお思いになってあれらの作品群を書かれたのではないかと、そう想います。それは祈りにも似た行為だったのではないでしょうか。
彼女のイタリア人のパートナーがあんなにも早く亡くならなければ須賀さんは、イタリアで日本文学翻訳者として活躍し続け、日本にイタリア文学を紹介し続けるイタリア文学者としてその生涯を送ったはずです。
しかし運命が彼女を日本へと送り返しました。それは彼女にとっては不幸ないきさつによるものでしたが、日本の読者にとっては幸福な出来事でした。作家・須賀敦子を日本は持つことができたのですから。
そしてその作品群をほぼ書き上げると彼女もまた「ひとり足早に歩み去った」のでした。
そこにこそ須賀敦子の作品を読む意味があるような気がします。
ある日本人がいて、ある外国文化と深く関わり、作家と「ならされ」そしてその深く哀しみに満ちた生涯を美しい日本語で表現し日本の読者に残してくれた。
それができて、作家としてそれ以上なにを求めることがあるでしょうか?たとえ短い生涯でもこれだけの仕事を残すことができた須賀敦子さんの幸福を祝福せずにはいられません。いまはただ須賀敦子さんの冥福を祈るばかりです。
【再録に当たって】
≪ドイツ生活ああだこうだ事典≫と銘打ちながら、「羊頭をかかげて狗肉を売る」ばかり、イタリアについてああだこうだしていたのでは、シナばかりを責めることはできませんね。
事のついでに、以前イザ版にアップした須賀敦子さんについてのエントリーを再録しておこうと思います。書いた本人に愛着のある文章の故です。
「登場したそのときからすでに完成された作家であった須賀敦子は、わずか八年間だったが「うかうかと人生をついやす」気配などみじんも見せず、旺盛な創作意欲を示しつづけて珠玉のごとき作品群を生み落とした。なのに突然、人にはとうてい忘れがたい記憶をとどめたというのに、自身はあの意思的に響く特徴ある靴音とともに、「アスファデロの白い花が咲く野」を、ひとり足早に歩み去ったのである。一九九八年三月二十日早朝であった。」
関川夏央氏が須賀敦子著『ヴェネチアの宿』文春文庫版の解説として記した文章の最後の部分の引用である。
ある時いきつけの日本書店でふとその表紙の美しさに惹かれ手に取ったその文庫版が、須賀敦子との出会いだった。その表紙で、船越桂氏の『澄みわたる距離』と題された彫刻がなにか特別な精神性をあたしに訴えかけていた。
関川氏は好きな文章家である、そう文章家というのがまさにふさわしい文章を書かれる作家とひそかに尊敬している。その関川氏のこの解説文を読んでこの文庫を買うことに決めた。
『ヴェネチアの宿』に収められた作品は、小説とも自伝ともつかぬ文章であった。がしかし小説とはなにか?よい小説はいつもそういう問いかけを読者に投げかける。その意味では、それらの作品は小説かも知れない。
読了して、作家のことを想った。いったいどういう人だったのだろうかと。その自伝的作品からその生まれた家の格式の高さと裕福さがわかる。まだ海外渡航が不自由なころフランスとイタリアに留学できたことでそれが知れる。また描かれた父上の様子からもそれがわかった。作家が、意思の強いそして感受性の鋭い明敏な頭脳の持ち主であることもわかった。
がしかし、それだけではない、この作家の何か他のものがあたしの心のどこかを静かにうち続けるのが感じられた。
もっとその作品を読まねばならぬ、そう思った。
それは作家が亡くなって数年たった後のことだった。海外に居住し、しばらく日本の文学とは離れた生活をしていたためその短い作家生活のことを迂闊にも知らなかったのである。