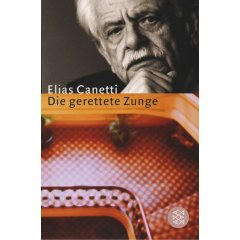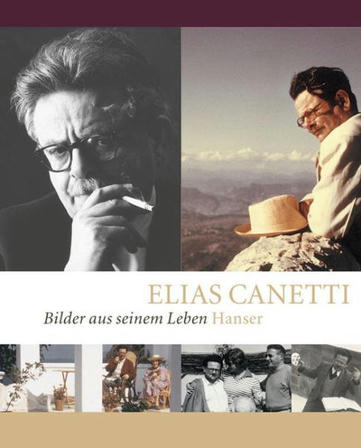| マルコおいちゃんのドイツ生活ああだこうだ事典 |
| ≪Bar di Marco≫から旧名に復帰しました。 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ドイツの「黒い森」(Schwarzwald)に発し、オーストリア、スロヴァキア、ハンガリー、スロベニア、クロアチア、ユーゴ・スラヴィア、ブルガリア、ルーマニア、モルダヴィアとつごう十カ国を流れて黒海にそそぐのが、かのドナウ河です。
ソ連・東欧の社会主義の崩壊後、あたらしい独立国と国境の再編があったので周辺流域の名前がすっかり変わってしまいました。
カネッティの生まれたブルガリアのルスチェク(Ruse)は、そのドナウの下流の港町です。
その生まれた町についてカネッティは、以下のように描写しています。
「この町はブルガリアにある、などと言ったりすれば、私はこの町について不十分なイメージを与えることになろう。というのも、そこには世にもさまざまな血統の人間たちが住んでいたし、一日に七ヶ国語ないし八ヶ国語を耳にすることも稀ではなかったからである。」
「しばしば田舎から来るブルガリア人たちのほかにもまだトルコ人たちがおり、この街に境を接してスパニオル街、つまり私たちの街があった。ギリシア人たち、アルバニア人たち、アルメニア人たち、ジプシーたちがいた。ドナウ河の対岸からはルーマニア人たちがやって来たし、私の乳母は・・・・もっとも彼女のことは覚えていないが・・・ルーマニア人であった。所によってはロシア人たちもいた。」
(自伝『救われた舌』(Die gerettete Zunge)、岩田行一訳、法政大学出版局、1981年)
なんとすさまじい状況ではないでしょうか?
交通の要衝ゆえのことでしょうが、そこには歴史的経緯もからみあっています。
トルコはかっての支配者、現在でもブルガリア国民の約10%がトルコ人です。ギリシア人は黒海貿易に従事し、祖国を喪失して流浪するアルメニア人も商業が得意です。
アルバニア人もバルカン半島南西部の故郷から西のイタリア、南のギリシア、東のブルガリアへとその貧しさゆえに移民をしているのでしょう。ジプシーはご存知の通り。ルーマニア、ロシアは隣邦です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%AA%E3%82%A2
それは何かヨーロッパのひとつの縮図のようにも見られます。
<続く>
多様性、それがヨーロッパを表現する一番よい言葉でしょう。
気候風土、言葉、食事、文化芸術どれをとっても各国、各民族でことなっています。しかしある一定の空気、山本七平流にいうある空気がヨーロッパにはあるようです。
それはそれぞれことなる各国・各民族をゆるやかに繋ぎ合わせるなにかです。よくヨーロッパの共通基盤として、キリスト教信仰、ローマ法などが指摘されますが、住んでみてわかるのは、そこにある、ある空気の存在です。
それへの検証はまたの機会にゆずるとして、さてそろそろこの稿を起すに至った「気がついたこと」について述べようと思います。
それは今年はじめのブルガリア、ルーマニア二カ国のEU参加によって思い出したことなのですが、それ以来『ヤダヤダ日記』で述べようとしていままで実現しなかったことなのです。
エリアス・カネッティ(Elias Canetti)は、1981年のノーベル文学賞受賞者です。
しかし彼については日本ではあまり注目されませんでした。
彼はブルガリア生まれのユダヤ人、しかもセファルディム(Sephardim)というスペイン系のユダヤ人の裕福な家庭に生まれ育ちました。
ゆえに母語はスペイン語を色濃く残すラディノ語、またはフデスモといわれる言葉でした。しかし、彼の父母がウイーン留学時代にしりあって結婚したため夫婦間の会話はドイツ語でなされ、その父母の秘密の会話への激しい興味からドイツ語を自己の言語として獲得します。そしてそのドイツ語で書いた諸作品によりノーベル文学賞受賞にいたったわけです。
この作家について知らしめてくれたのは家内でした。知り合ってまもなくのころお互いの意思疎通をシナ語にたよっていた二人をカネッティの両親に例えての冗談としてでした。
現在、ドイツ人が夏の休暇先にでかける先ベスト・ワンはマヨルカ島でしょうか?
以前はイタリア、ギリシャが人気のあった保養先でしたが、現地の物価上昇とともに人気も落ちているようです。
トルコも値段が安いほうなので人気は高いのですが、モスレムを嫌って敬遠する人もやはりいるようです。同じ理由で、チェニジアも今ひとつ人気がもり上がりません。
上記した場所はすべて訪れていますが、いずこも言葉で困ったことはありません。現地の人がみなドイツ語ができることが多いからです。というのも、これらの国々からドイツへ出稼ぎにきた人々が多く、ある程度稼いで帰国し、ドイツ人相手のペンションなどを経営する例が多いからです。
しかし、せっかく外国へいってドイツ語で押し通すのも便利とはいえ、なにか味気ないものです。
そこでせめて片言でも習おうとするのは普通でしょう。また簡単な挨拶程度でもできると現地での扱いがめだってかわってくるのは、やはり人情というものでしょうか。
例えば、家内の家族はみなそれぞれ以下のような外国語を話しますが、それも家族ですごした休暇の跡をのこしていてほほえましいものです。
得意とする外国語の順に列記します。
【義母】イタリア語、英語
【長姉】フランス語、イタリア語、英語
【長兄】イタリア語、英語
【次姉】英語、フランス語
【三姉】英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
【家内】英語、フランス語、イタリア語、北京語、日本語、オランダ語
みな英語ができるのは、高校卒業資格必修科目だからです。その他の外国語にはよく行く休暇先と専門とする職業が反映されています。
前回、フランス・アルザス地方の特殊事情を紹介しましたが、首都パリでも以前ほどはフランス語中心主義ではなくなっています。
店に入ってフランス語ができないから英語、またはドイツ語でしつこく話していると、それなりの対応力のあるものが何処からかでてくるのが痛快です。
まあ、こっちはお客だからそうなのかもしれません。たとえばお役所なんぞはあいもかわらずの対応なのでしょう。
しかし徐々に氷がとけ始めてはいるのでしょう。またEU各国、とくに独仏の間ではそれなりの努力がなされているのです。
たとえば独仏軍の創設。独仏共同経営のTV局。高校生の相互交換ホームステイ。などなど地道な相互理解が深まっているからこそのことでしょう。
また人・物・金が自由に流通するようになってからは、人の行き来がより頻繁になり週末に旧「国境」を越えて他国に買い物に行くのはあたりまえになってもいます。
われわれ家族も時には、香港式の「乳猪」(子豚のグリル、皮がぱりっとして肉が柔らかく美味)を食しにオランダへ赴くこともあります。
ユーロが導入されてからは面倒な換金の手間もないのでより気楽に「越境」することになりました。
そのさい、以前は気をつかって英語を話すようこころがけていましたが、今はすこし面の皮を厚くしてドイツ語で押し通してしまいます。
つまり前回にのべたフランス言語帝国主義のドイツ版をみずから演じてしまっているわけです。
もっともそれは各地の休暇先でドイツ人がとる態度そのものなので、ふと赤面したくなるときもあります。
<続く>
おまけ
勿忘草(Vorgiß mein nicht = Forget me not)
春の花々を少しやすんで、気がついたことについて述べておこうと思います。
EU成立(1995年)以来の、欧州における多元語化についてです。
たとえばフランスは言語「帝国主義」で、どこにいってもフランス語を使用し、他国人がフランス語を話すことを強要する、という態度でした。フランス国内においてはもちろんそうで、しかも正しいフランス語をしゃべらないと相手にもしない、という高慢さがよく話題になったものです。
しかし今ではその気風もやや緩んできているように思われます。
少し前にストラスブールにいった時のことです。その街は、かってはドイツに属していたアルザス地方の首都であること皆さんご存知のことと思います。
アルザスは、ナポレオンによりフランスに強奪され、ビスマルクが普仏戦争で取り戻し、第一次世界大戦でフランスに帰り、またナチ政権が取り戻し、という具合に常に独仏両国の争奪にあってきた地方でした。
アルザス人はドイツ系フランス人です。一度、現地のカフェーで土地の老人達がドイツ語でだべっているのを耳にしました。それはドイツ語にフランス語の語彙をまぜた奇矯な言葉でした。
さてストラスーブールでのことです。こっちはあいにくフランス語ができません。家内がいれば通訳してくれますが、ある日一人で買い物に出かけました。
店にはいって物色しているとむこうでは必ず「何をお探しで」と店員から声がかかります。
すかさずドイツ語で、「フランス語は話せません、誰かドイツ語のできる人はいますか?」と尋ねると、その人がドイツ系のこともあり、またフランス系の場合は、同僚でドイツ系あるいはドイツ語のできるものを呼び寄せます。
その結果わかったのは、たいがいどんな店にも誰かドイツ語のできるものがいるということです。しかも若いフランス人なら片言でもドイツ語を話せるのです。
これはアルザス地方特有の現象かもしれませんが、かってはドイツ語教育が公式の学校ではなされていなかったことを考えると大きな変化です。
<続く>
おまけ
Schlüsselblume(Schlüssel>鍵、Blume>花。詳しくは稿をあらためて)
この花をだむエリちゃんに捧げます。日夜、嫌韓流にお励みのことゆえお疲れでしょう。少しでも鬱陶しい疲れが癒されますように。