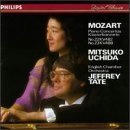| マルコおいちゃんのドイツ生活ああだこうだ事典 |
| ≪Bar di Marco≫から旧名に復帰しました。 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
前回、ちらとふれたピッザの老舗・≪Da Michele≫を紹介しましょう。
ナポリも中心街、といってもナポリ大学からウムベルト一世通りを中央駅にむかった、あまり上等とはいえない一角にその店はあります。写真のように住宅の一階、じつにささやかな店なのです。
しかし、いつ行っても行列。その頑固な営業方針が世界中に知れ渡っているのか、行列する人々もさまざま。とくに米国なまりの英語が耳障りなほど、多く聞こえてくるようです。
古代ギリシア植民地であったころから近代のフランス植民地時代まで、大いに栄えたナポリですが、イタリア統一以後、貧窮した街になりさがり、多くの貧民を移民として南北アメリカへ送り出しました。
その後裔たちが里帰りしていることもあるのでしょう。
さてその店は、中の広さがせいぜい20平方メートルといったところでしょうか?
入り口を入ると正面にオーブンが鎮座しているのが見えます。もちろんオリーブの薪を使用します。
席は、五人がけ程度のベンチ式の椅子席をもつ長いテーブルが、左側に平行して二つ。右側にひとつ。ですからおよそ三十人で満員というところでしょうか?
左のテーブル席に面して、つまりオーブンにむかって左側に三人の職人が、客席にむかってまるで舞台の役者のように、しかしただ黙々と仕事をしています。
そのうしろ左の壁際で、粉をこね、まるめ、ひらたく伸ばす職人がいて、ひろげた生地をさきの三人のうち一番左側の男にわたします。するとその男は生地の上にトマトを盛り付けて、真ん中の男にわたします。
どうもそれが主人であるらしく、ものものしい威厳にみちた顔つきで、その上にモッツアレラを盛り付けます。そしてバジリコ。
右の男がそれをヘラでうけてオーブンの中へ。
さてこれが、前工程です。
<続く>
ピッザの本場といえば、いわずと知れたナポリです。
ナポリのピッザは、ほんとうに他の地方のピッザとは違います。もとより日本のものとは、もう画然と異なる食物であると断言しておきましょう。
まず、ピッザの生地がちがいます。弾力のある、焼きあがったばかりのその香りはちょうど日本のお餅が焼けたような、食感も歯ごたえのあるモチモチした感じ。
生地を内側を薄く、外側を厚く広げるのも、またちとちがいます。大きさも、そうだいたい直径40cmはあるでしょうか?
のせるトマトがすこしすっぱめの味がしますし、なんといってもモッツアレラがちがいます。念のため申し添えておきますが、ピッザにはモッツアレラ以外のチーズを使用するのはご法度ですよ。もし黄色いゴーダ・チーズがのっていたら、即「あっ、これ贋物」といってやりましょう。さらに新鮮なバジリコの葉っぱがのります。
このトマトの赤、モッツアレラの白、バジリコの緑であらわすのがイタリアの国旗、世に言う「ピッザ・マルゲリータ」(Pizza Margherita)がこれです。そして、それですべてです。
ナポリでピッザといえば、このピッザ・マルゲリータしかなく、あとはすべて邪道(といわれています)。
もちろん、妥協の道はいくらでもあるわけで、街には種種雑多なピッザがあふれています。あふれてはおりますが、正しいピッザといえば、ピッザ・マルゲリータにつきる(ということになっています)。
老舗の≪Da Michele≫は、頑固にこのマルゲリータだけを給するので有名です。店には、「頭のいたくなるような難しいピッザは作りません。マルゲリータとマリナーラだけだよ」と店主の断り書きが貼りだしてあります。
その心意気やよし。で、マリナーラ(Mrinara)とは、モッツアレラをのぞいて、かわりにつぶしたニンニクをのせるものです。これを別名、「ピッザ・ナポリターナ」と現地では称します。
つまり、マルゲリータがあまりにも有名になってしまいましたが、実は本場中の本場・ナポリのピッザは、マリナーラに止めを刺すのですよ。
皆さん、よく覚えて知らない人に知ったかぶりをしてくださいね。
このシリーズもこっちに引っ越すことにしました。
この前は、はやまってもう夏に聴く音楽をやっつけてしまいましたが、やはり春に聴く音楽も補習しておきましょう。
あるのかないのかよくわからないドイツの春。先々週は30度をこえる夏日、先週は20度前後にもどってすずしく感じたほどでしたが、今週はまた気温は上昇気味、明日からはまた30度になりそうだと、天気予報は伝えています。
そんな具合ですから、新緑も例年より早くでそろい、森はもう輝くばかりの緑です。
いつか写真をアップしましょう。
さて、春にふさわしい音楽といえば、そうモーツアルトです。
モーツアルトならなんでもいいわけです。ピアノ・ソナタもいいし、ピアノ協奏曲、オペラ、交響曲、ほんとになにを聴いてもモーツアルトの音楽には春風が吹いているようです。しかし生命あふれる春にも、春の哀しみがあるように、モーツアルトの音楽にも美しさい軽さのなかに吹きすぎるひとすじの哀しみがあります。それゆえに、人々から深く愛されるのでしょう。
『ピアノ協奏曲第23番、イ長調、K488(Klavierkonzerte A dur, Nr.23, K488)』
とくに第二楽章のはじめの部分の深々とした哀しみはどうでしょう。この部分をいかにデリケートに響かせるかでピアニストの腕前がわかります。
昔ならクララ・ハスキルがモーツアルト弾きとして高名で、いまでもファンは多いと思いますが、なにしろ古い時代のことゆえ録音がよくありません。
いまなら、たぶん内田光子でしょうか?彼女の父上は外交官で、ご自分も英国を中心に活動されています。実は、一度だけドイツのある街角で彼女とすれちがったことがあります。憂いを含んだその面影は、きっと多くの哀しみを知る方だと思います。それゆえか、モーツアルトでも短調の曲によくその真価を発揮されるようです。
K488は長調の曲ですが、第二楽章は短調のせいか彼女にはぴったりです。
まだお聴きでない方はぜひご試聴ください。きっと魅せられるはずです。
カネッティの両親はヴィーン留学中にしりあい、二人の会話はドイツ語で行っていたことは以前にふれました。
カネッティは以下のように書いています。
「両親が対話を始めるとき、自分が除け者にされていると感じる正当な根拠があった。彼らはその際非常に生き生きとして来て陽気になったのであり、私は自分がはっきり感じとったこの変身をドイツ語の響きに結びつけた。私はこの上もなく緊張しながら彼らの話に耳を傾け、それからあれこれの単語が何を意味するかを彼らに尋ねた。彼らは笑いながら、そういうことはお前にはまだ早すぎる、お前がもっと大きくならなければ理解できないようなことだ、と言った。」
この特殊な言語環境が、彼をドイツ語にひきつけることになったのが容易に想像されます。それは自己のよってきたる者達の秘密の会話に用いられる言語であり、また男女の愛という子供にとっては不可思議な世界への鍵でもあったのですから。
その後、両親は祖父母たちの反対をおしきり子供たちを連れ英国へと移住しますが、そこで不幸にも父が突然死してしまいます。
母は、さらにヴィーンへの移住を決心し、学業のために必須であるドイツ語を幼い息子に自ら教授することになります。
カネッティにとっての、その喜びたるやいうまでもないでしょう。彼はついに秘密にみちた憧れの言語を手にすることができたからです。しかも父に代わって保護者となるべき対象たるその母親から直接教授されることにもなったのですから。十分な誇りさえ手に入れることになりました。
このようにドイツ語を獲得できたことを、彼は「救われた舌」と表現しました。
家内によると、カネッティのドイツ語表現は実に美しいものだそうですが、あたしにはあいにくそこまで読み取る力がありません。
ただ彼をめぐる言語の状況に驚きを覚えるとともに、言語と言語表現をめぐるさまざま形に強く興味を惹かれます。
カネッティについては、これくらいに止めて、自己の言語生活をめぐって話を進めようと思います。
<続く>

Goldbackとミツバチ
『ヤダヤダ日記』では、「エトランゼ」というシリーズで何回か、ドイツに住む外国人のことを取り上げてきました。
http://marco-germany.iza.ne.jp/blog/folder/16642/
今回から、そのシリーズはシナ関係を除き、こちらで継続することにしました。
カネッティの話で、アルバニア人についての言及がありましたので、あたしの知るアルバニア人についてふれておこうと思います。
例によって、かっての同僚です。今回は二人登場してもらいます。B君とC君です。Aはあたしです。会話はあたしがまだ別の会社で勤めていたころの事を回想して組み立てました。
A> えっと、君たちがドイツにきたのは、お父さんの世代だったね。
B> そうだよ、僕の父がまずドイツへ出稼ぎにきたわけだ。
A> じゃあ、君はドイツ生まれだね。
B> そのとおり。でもCはちがう。
C> 僕の場合はちょっとちがう。僕の家内は、Bの妹なんだ。つまり僕たちは義兄弟になる。結婚してからドイツに来た。
A> えっと、するとB君の妹さんもドイツ生まれだね?
C> そう、しかもBと同様にドイツ国籍をすでにもっている。Bの父親と僕の父親は友人で、その縁で僕もドイツに働きにくるようになったわけだ。
A> 君たちは、マケドニアのアルバニア人だけど。マケドニアにはどれくらいのアルバニア人が住んでるの?
B> およそ半分ほどだろうね。
A> で、みんなモスレムかい?
B,C> もちろん。
A> でもお父さんが来られたころは、まだユーゴ・スラヴィアだったね?
B> そのとおり。失業中にユーゴの職安でドイツ行きを薦められたそうだ。当時は両国でそういう協定があったんだね。
A> なるほどね。ところで、アルバニア本国やコソボ、あるいはイタリアにすむアルバニア人同士でなにかネット・ワークはあるのかい?
C> アルバニア本国は、マケドニアの隣だからもちろん情報ははいってくる。スターリン主義のころは、いちはやく改革をはじめたユーゴにすむ我々は同情して心を痛めていたと、父たちがいつも言っていた。
B> 僕は、こっちでイタリアから来た同胞に空手を習ったんだよ。でも師匠はイタリア語しか話せない。
A> へえ、何流だい?
B> ショートーカンというのだけど、知ってるかい?
A> たぶん松涛館流のことだろうね。「ショートー」とは、松の木に吹き付ける風の音、という意味だよね。「カン」は家とかホールという意味だよ。オス!
B> へえ、そうだったのか?オス!
A> で、なぜ空手を?
B> やはり子ども時代はいじめられたからね。強くなりたかったわけさ、それだけ。
A> では、アルバニア人どうしで結束する組織があるわけかな?
C> そうたいしたものじゃない。でもモスレム同士だし、言葉や風俗の関係で自然と集まって助け合うのはいいことじゃないか?日本人は?
A> もちろん、そうだけど。日本人はそれほどじゃない。みんな会社派遣の人が多いし、会社が彼らをまとめる単位じゃないかな?
B> すると君の場合は?
A> つまり日本人とはあまり付き合いがない、というわけさ。
C> さみしくないかい?
A> 君たちとこうしてつきあうのも楽しいよ。
B> オス!(笑)
A> オス!(笑)

http://abroad.hotel.travel.yahoo.co.jp/images/maps/albania.gif